事務所など業務用でよく使われている直管型蛍光灯のFL40W。
これのLED化を最近多く行っております。
ところがこの直管タイプのLED化はちょっと注意が必要です。
電球のように、ソケットが同じだからと、すぐには交換できないのです。
蛍光灯の器具の中には安定器と呼ばれる部品が内臓されています。
これによって高電圧を発生させ電子を放っているのです。
蛍光灯の中を電子が飛び交っていてこれが光って見えるのです。
ところがLEDは直流と呼ばれる電流を使っています。
ご存じのように、蛍光灯の器具は交流です。 これを直流に変換しなければLEDは光らないのです。
(ちなみに電球型は、あのヒダヒダ部に直流変換機が内蔵されています)
一般的に大手のメーカーさんから発売されている直管型LEDは、この直流変換機とランプは別になっています。
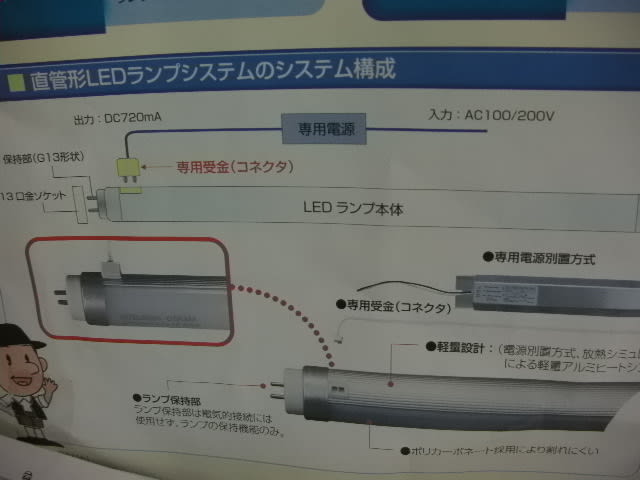
ところが、ネットで流通しているメーカーさんのは、電源内臓型をウリに販売されています。
この点をよく質問されます。
なぜ、大手メーカー製はLEDと電源が分かれているのか?
蛍光灯のピンが両端にある口金の規格はG13と呼ばれています。

この口金は、ランプを支える用途と、電気を流す2つの役割があります。
実は、このG13という規格には500gまでという重量制限があります。
電源内臓タイプは当然重くなります。 もちろん各メーカーはこれ以内の重量に抑えてありますが、従来の蛍光灯に比べて重くなるので、不安があります。
この辺が大手メーカーさんは嫌っているのでしょう。
この細いピンだと心細い気がしますね。

もう一つは電流を流す端子の問題。
我々がよく、蛍光灯が点灯しない という事で訪問すると、端子の接触不良というのがよくあります。
今まで使っていたG13の口金をそのまま流用というのは、大手メーカーさんはリスクが多すぎます。 クレームの元です。
そこで、口金も新しく交換するような仕様になっているのです。
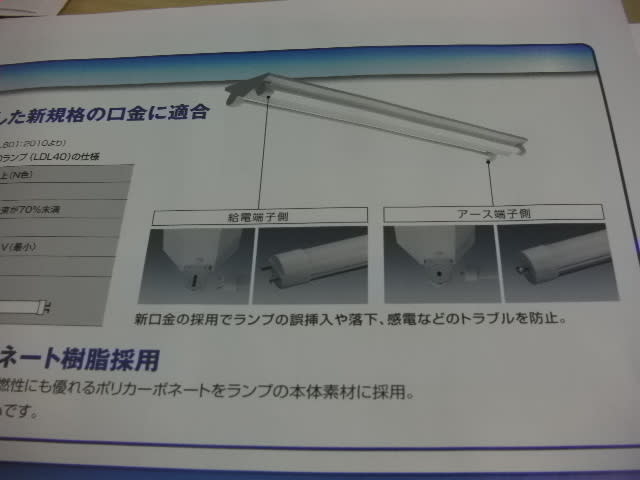
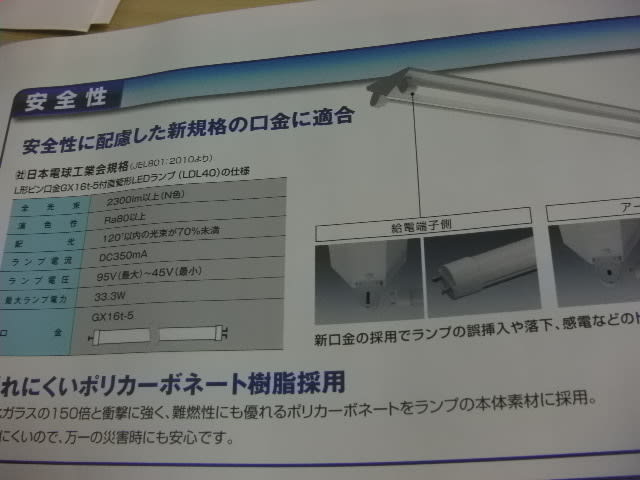
また、LEDが切れたら、ランプだけを交換できるか? と聞かれます。
ここがLEDの考え方の違うところ。
LED器具を構成している器具の中で、壊れる場所は電源部です。LEDという発光ダイオードはあまり壊れません。
LEDが壊れる前に、電源部のコンデンサーが壊れるのです。
一般的に10年と言われているのは、LED(発光ダイオード)の寿命じゃなくて、電源部のコンデンサーなのです。
もしかしたら、10年後 私の仕事は『LEDはそのまま使えるから、中の電源を交換しますね』
なんて言ってるかもしれません。
読んで頂きありがとうございます。
以下のバナーを押して頂くと、私の励みとなります。
![]() にほんブログ村
にほんブログ村
![]() にほんブログ村
にほんブログ村
ご協力ありがとうございます。